~確実で安心な遺産承継のために、公正証書遺言という選択~
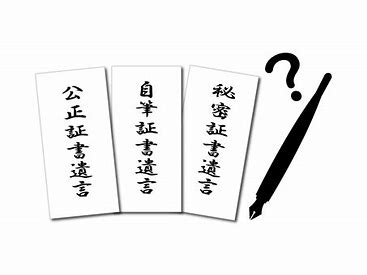
遺言能力と年齢要件
遺言書は、誰でもいつでも書けるわけではありません。民法では「満15歳以上で、意思能力を有する者」が遺言をすることができると定められています。この「意思能力」とは、自分が何をしているのか、その行為によってどのような結果が生じるのかを理解・判断できる能力を指します。
高齢であっても意思能力がしっかりしていれば遺言書は作成できますが、認知症などで判断能力が失われてしまうと無効になります。症状が軽く、意思能力があると判断される時期であれば、公証人が面前でその能力を確認し「公正証書遺言」を作成できる場合もあります。ただし、この判断は医師や公証人による個別判断に委ねられるため、「まだ大丈夫」と思っているうちに作成しておくことが大切です。なお、意思能力を欠くと、銀行預金の引き出しなど多くの法律行為が制限されるケースもあります。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書には、大きく分けて「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。特別方式は病気や船舶内などの緊急時に限られるため、通常は利用されません。また、秘密証書遺言を選ぶケースも少ないのが実情です。ここでは、一般的に利用される「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について説明します。
- 公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言書です。本人が口述した内容を公証人が文章にまとめ、公証人と証人2名の立会いのもとで署名押印します。原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がなく、検認も不要で、最も安全かつ確実な方法です。特に相続トラブルを避けたい方や、迅速に遺産承継を進めたい方に強くおすすめします。 - 自筆証書遺言
全文・日付・氏名を自筆し押印する方式です。費用がかからず手軽に作成できますが、方式不備や紛失・改ざんのリスクがあります。法改正により、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳コピーを添付したりすることが可能となり、利便性が向上しました。
検認手続きの概要
自筆証書遺言や秘密証書遺言を相続手続きに使用する場合、家庭裁判所での「検認手続き」が必要です。検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぎ、その存在と形式を確認するための手続きです。
申立てから検認期日までには通常1~2か月程度かかり、その間は遺産分割や名義変更などの手続きを進めることができません。検認では、相続人全員が呼び出され、家庭裁判所で遺言書が開封され、内容が確認・記録されます。これは遺言の有効性を判断するものではなく、あくまで形式的な確認ですが、相続開始後の手続きを遅らせる要因となります。
一方、公正証書遺言であれば検認は不要なため、相続開始後すぐに遺産承継の手続きを進められます。この差は、残された家族の負担や手続きのスピードに大きく影響します。
自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言を作成する場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用することをおすすめします。原本を法務局で保管することで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、相続開始後の検認手続きも不要となります。費用も低額で済み、確実性が高まります。
まとめ
遺言書は、財産を巡る争いを防ぎ、残された家族の負担を軽くするための大切な手段です。有効な遺言のためには「遺言能力」が欠かせず、作成のタイミングを逃すと手続きはできなくなります。
検認不要の公正証書遺言がもっとも確実ですが、自筆証書遺言でも保管制度を利用すれば安心度が大きく高まります。
確実で安心な遺産承継を実現するため、早めの準備をおすすめします。さらに、遺言書の内容は家族構成や財産状況の変化に応じて見直すことが望ましいため、機会があるごとに確認・修正することを心がけましょう。
【免責事項】
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。記載には十分配慮しておりますが、法改正等により最新でない可能性があります。具体的なご相談やお手続きは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、掲載内容に誤りや不適切な表現等がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。内容を確認の上、必要に応じて速やかに対応いたします。