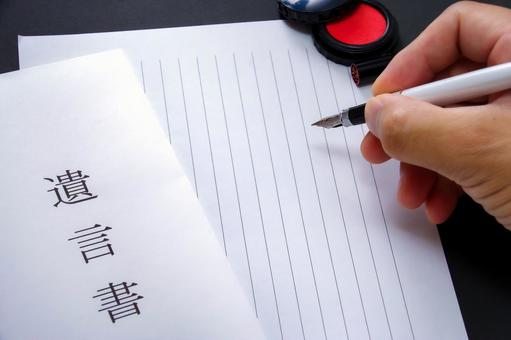
遺言書に記載できる内容は、大きく分けて「遺言事項」と「付言事項」の2種類があります。
遺言事項とは
「遺言事項」とは、法律上、遺言によってのみ効力を発する事柄で、法的拘束力を持ちます。遺言書に記載する際に特に注意すべき主な遺言事項は、以下の3点です。
• 相続分や遺産分割方法の指定・遺贈遺産を誰に・どのように分けるかを指定できます。これにより、法定相続分とは異なる分け方も可能になります。
• 遺言執行者の指定遺言の内容を実現するための手続きを担う人物を指定することで、相続人間の利害調整を円滑に進められます。第三者を選任することも可能です。
• 祭祀承継者(主宰者)の指定お墓や仏壇の管理を誰に託すかを明確にしておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
これらの事項は、いずれも相続手続きに直接影響を与えるため、遺言書作成時には慎重に検討することが重要です。
付言事項とは
「付言事項」は法的効力はありませんが、遺族に対する感謝の気持ちや遺言に込めた意図・希望を伝える文章であり、相続人間の感情的な対立を和らげる効果があります。そのため、「円満相続のカギ」として非常に重要な役割を果たします。
特に、法定相続分と異なる内容を定めた場合や、特定の相続人に多くの財産を託す場合、その理由や想いを丁寧に付言事項で説明することが望まれます。したがって、遺言書には可能な限り付言事項を盛り込むことを強くお勧めします。
なお、記載できる内容は他にもありますが、すべてを網羅する必要はなく、個々の事情や意図に応じて必要な項目を盛り込むことが大切です。
具体例と書き方の注意点
遺言書を作成する際は、法的効力を確保し、遺産分割に関するトラブルを未然に防ぐために、いくつかの重要な点に注意する必要があります。特に、予備的遺言や不動産の相続・遺贈など、特定の事情に関しては慎重に記載しなければなりません。以下に遺言書作成時の留意点を挙げます。
- 予備的遺言の記載
• 予備的遺言とは: 主要な遺言が無効になった場合に備えて、代わりとなる遺言を記載することを意味します。予備的遺言を入れておくことで、主要遺言の内容が何らかの理由で無効となっても、その代わりの内容に従って遺産分割を行うことができます。
• 注意点: 予備的遺言を記載する際、主要遺言と矛盾しないように内容を整合させる必要があります。例えば、「もしも〇〇が無効であれば、次に〇〇を遺贈する」と明確に記載し、予備的遺言が発動する条件を具体的に記載することが重要です。
• - 書き方に注意が必要な相続・遺贈の記載
相続や遺贈に関する記載には、書き方(表記方法)に特に注意が必要です。具体的な財産について記載する際には、詳細な情報を正確に記載しないと、法的効力が認められない場合があります。
例えば、不動産の相続や遺贈を行う際には、登記簿に記載された表題部の内容(名称、所在、面積、地番など)を正確に記載する必要があります。このような記載ミスがあると、後の相続登記や手続きで問題が生じる可能性があります。しかし、不動産に限らず、動産やその他の財産についても、詳細な情報を明記することが重要です。
• 注意点: 相続や遺贈する財産については、「土地」や「建物」といった一般的な表現ではなく、できるだけ具体的に記載することが大切です。これにより、遺産分割協議を避け、相続や遺贈が確実に実行されるようにすることができます。
このように、相続や遺贈に関して具体的な財産の記載方法には十分な注意を払い、誤解を招かないように記載することが法的効力を確保するために重要です。
- 相続人以外への遺贈(遺産分割の問題)
• 遺言書で相続人以外に遺贈を行う場合、遺留分(最低限の相続分)に配慮する必要があります。遺言書によって遺産を指定された者が、法定相続人の遺留分を侵害する形になる場合、遺留分を侵害された相続人から異議申し立てがされることがあります。
• 注意点: 遺言書作成時には、遺言書に記載した内容が遺留分に影響を及ぼさないかを確認し、場合によっては遺言書に遺留分の侵害を避けるための配慮を盛り込むことが重要です。
• - 署名・押印の不備に注意
• 遺言書は、遺言者本人が署名し、押印をしない限り法的効力が認められません。特に自筆証書遺言の場合、日付や署名を省略することが多いため、必ず遺言者本人の署名と押印が必要です。
• 注意点: 日付が不明確だと、遺言書の内容が先の遺言を撤回するものとして取り扱われない場合があるため、日付は必ず明記し、署名や押印の手続きを確実に行うことが大切です。