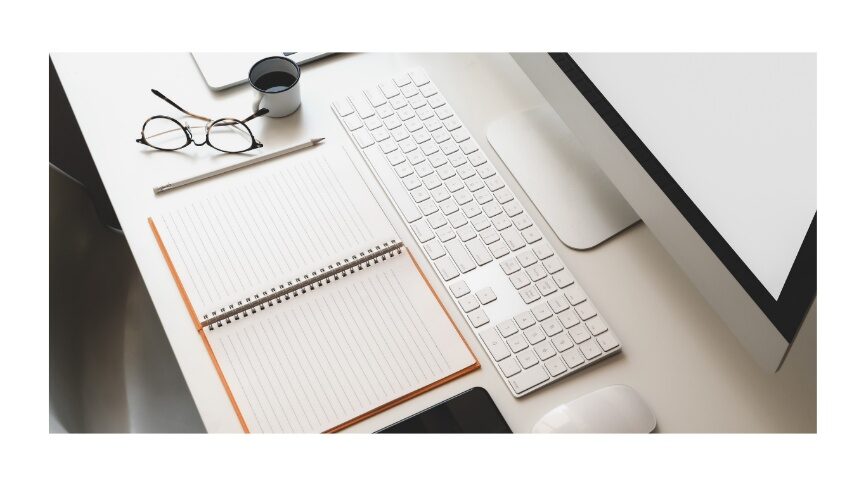
作成を勧めたいケース
【1. 相続人の構成・関係に課題がある場合】
① 子どもがいない人
• 相続人が兄弟姉妹や甥姪まで広がるため、配偶者と血縁側の調整が難しい。
• 兄弟姉妹と配偶者の遺産分割協議は心理的負担が大きい。
② 再婚・複雑な家族構成の人
• 前妻(夫)やその子との関係、いわゆる「連れ子」間の関係が悪いと相続争いが起こりやすい。
• 先妻(夫)や愛人との間に認知済みの子がいる場合も含む。
③ 内縁の配偶者がいる人
• 法律上は相続権がないため、遺贈による保護が必要。
④ 相続人と不仲・絶縁・音信不通の場合
• 遺産を渡したくない相手がいる場合、相続分の指定や相続人廃除を検討。
• 連絡の取れない相続人がいると遺産分割協議が成立しないため、遺言により回避可能。
⑤ 相続人が遠方または海外にいる場合
• 遺産分割協議の調整が困難。
• 海外相続人・海外資産がある場合は国際相続の視点から遺言が不可欠。
【2. 相続人がいない/指定したい人がいる場合】
⑥ 相続人がいない人(おひとりさま)
• 遺産は国庫に帰属。お世話になった人や団体に残したい場合、遺言が必要。
⑦ 法定相続人以外の人・団体に遺したい場合
• 内縁配偶者、孫、嫁・婿、友人、介護してくれた人、NPOなど。
• 法定相続人ではないため、遺贈の形で指定する必要がある。
⑧ 特定の人に重点的に相続させたい場合
• 介護・支援をしてくれた子ども等に多くを遺したいときは、明確な指定が必要。
【3. 財産や事業の性質に問題がある場合】
⑨ 遺産の大半が不動産の場合
• 共有になるとトラブルの元。誰に渡すかを指定しておく必要がある。
• 居住権や使用権も含めて明記すべき。
⑩ 特定の財産(墓地、仏壇、家業用土地など)を承継させたい場合
• 思い入れや管理の必要がある財産については、遺言での承継先指定が有効。
⑪ 事業や農業の承継を予定している場合
• 株式の分散や農地の分割により事業が立ち行かなくなるリスク。
• 後継者の指定や、承継の具体的方法を遺言で明記する必要がある。
⑫ 海外資産・外国籍を有する場合
• 各国の相続制度が異なるため、国際的な視点で遺言が不可欠。
【4. 生活・福祉への配慮が必要な場合】
⑬ 認知症・知的障害・精神障害を持つ家族がいる場合
• 配慮ある分配や信託型遺言も検討対象。
• 成年後見制度との関係も含めて計画的対応が必要。
⑭ 配偶者の生活を守りたい場合
• 高齢・収入がない・病気がちなど、配偶者を優先的に守りたいときは遺言での明確な意思表示が有効。
⑮ ペットがいる場合
• ペットは法的には「物」。面倒を見てくれる人と費用を指定しておくと安心。
【5. その他】
⑯ 相続人が多数いる/財産内容が複雑な場合
• 調整が難航しやすいので「誰に何を」明記しておくことで円滑化。
⑰ 遺産を社会・福祉・教育などに寄付したい場合
• 法定相続人がいない、または少額だけ残し寄付したい場合は遺言で必ず指定を。
【免責事項】
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。記載には十分配慮しておりますが、法改正等により最新でない可能性があります。具体的なご相談やお手続きは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、掲載内容に誤りや不適切な表現等がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。内容を確認の上、必要に応じて速やかに対応いたします。