~遺言書は“今あるもの”を見つめ直す機会でもあります。~
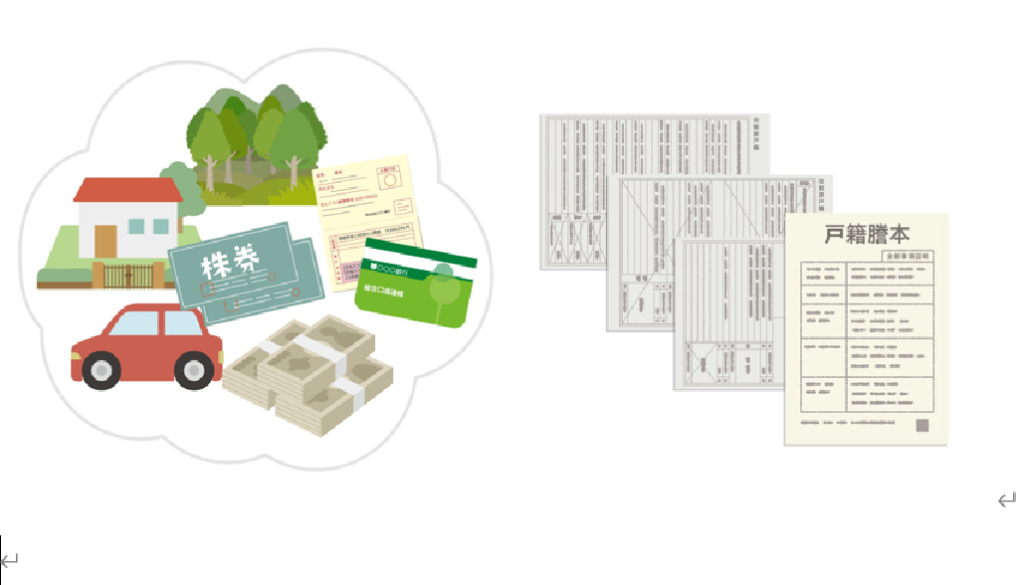
遺言書を作成するとき、多くの方は「誰に何を遺すか」をまず考えます。しかし実際には、その前に欠かせない準備があります。それが 「相続人」と「相続財産」の調査 です。この作業を怠ると、せっかく作った遺言書が無効になったり、家族間のトラブルの原因になったりすることがあります。ここでは、なぜこの調査が必要なのか、そしてどの程度の正確性が求められるのかを整理してみましょう。
相続手続きと遺言書作成における調査の違い
相続手続きでは、すでに相続が発生した後に「誰が」「何を」相続するかを確定させるため、相続財産の調査を行います。これは法律上の要件であり、誤りがあると登記や名義変更ができません。つまり、相続手続きにおける調査は 「事実を確定するための作業」 です。
遺言書作成で調査が必要な理由
一方、遺言書作成時の調査は「完全無欠」である必要はありません。可能な範囲で戸籍や相続財産を確認し、できる限り正確性を期すことが大切です。事後に新たな相続人や財産が見つかった場合は、遺言の修正や補足が必要になることもありますので注意が必要です。
遺言書作成時に調査を行う主な理由は、次の4つです。
① 相続人の把握および相続関係の明確化のため
実際の戸籍を確認せず、相続人の範囲や法定相続分を正確に理解しないまま遺言を作ると、思わぬ相続人の漏れが起きることがあります。たとえば、行方不明者や認知相続人、先妻の子などがいる場合は、戸籍の収集による確認が欠かせません。調査を行うことで、法的に正確な相続関係を前提とした遺言内容の作成が可能になります。
② 相続財産の全体像を把握するため
遺言書で相続財産の分配を指示する際には、その対象となる財産の内容と範囲を正確に把握しておく必要があります。不動産や預貯金、有価証券などの調査を怠ると、記載漏れや重複が生じ、後の手続きで混乱が起きることがあります。正確な相続財産の調査は、遺言書の信頼性と実効性を高める基盤となります。
③ 遺言の意図や効果を正確に反映し、争いを防ぐため
相続人や相続財産の実態が明確であれば、遺言書の内容も実際の状況に即したものとなり、誤解や不公平感を減らせます。これは、いわゆる「争族」防止の最も有効な手段のひとつです。事実関係を正確に把握しておくことで、被相続人の意思が確実に実現され、遺言執行時の混乱も避けられます。
④ 相続税対策上の正確性確保のため
遺言書は、相続税の負担を考慮した資産配分を行う際にも重要な役割を持ちます。そのためには、資産だけでなく借入金や保証債務といった負債も含めて把握しておくことが必要です。正確な相続財産の調査は、相続税対策の前提条件でもあります。
行政書士がサポートできること
行政書士は、戸籍調査による相続人の確定、相続財産目録の作成、遺留分を考慮した文案支援などを通じて、遺言書作成を法的・実務的にサポートします。また、公正証書遺言の作成時には、公証人との調整や必要資料の整理も行うことが可能です。専門家の関与によって、「想いが確実に届く遺言書」を残すことができます。
まとめ
遺言書作成は、単に「想いを書き残す」だけでなく、家族の未来を見据えた法的準備です。正確な調査と適切な記載のバランスが、遺言の実効性を左右します。行政書士の支援を受けながら、今のうちに安心して準備を始めましょう。
【免責事項】
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。記載には十分配慮しておりますが、法改正等により最新でない可能性があります。具体的なご相談やお手続きは、当事務所までお気軽にお問い合わせください。また、掲載内容に誤りや不適切な表現等がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。内容を確認の上、必要に応じて速やかに対応いたします。